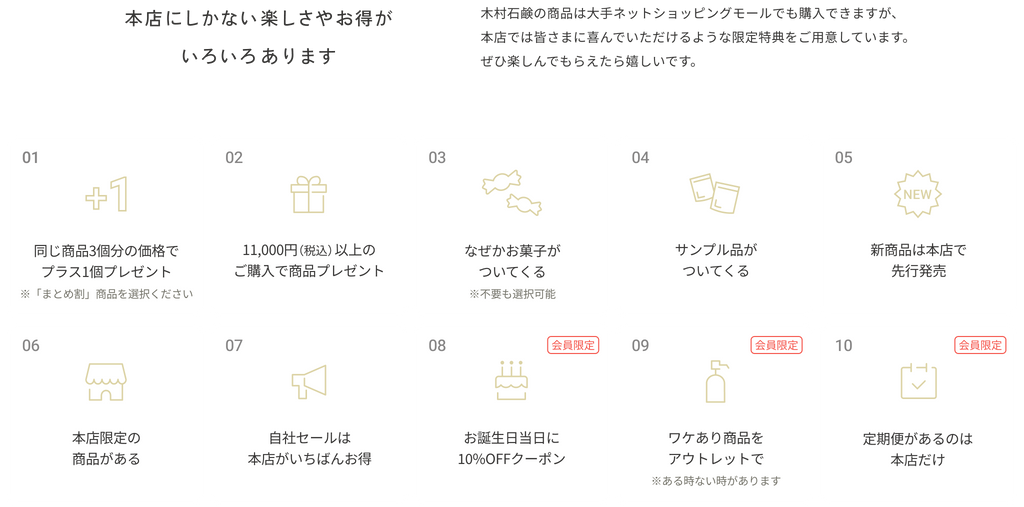インタビュー
「ご縁」から仕事が生まれゆくショップ&ブランド運営を——京屋染物店
京屋染物店の蜂屋さんに取材させていただきました!

書き手:うらちゃん
書き手:Masashi Sasaki|佐々木将史
大正7年(1918年)に創業した、岩手県一関市の「京屋染物店」。染物屋としての100年を超える伝統を引き継ぎつつ、新しいことにも積極的にチャレンジをしている会社です。
若者も注目する、伝統技術を活かした「縁日」のシャツやもんぺはどのように生まれたのか。木村石鹸の『12/JU-NI』をはじめ、他ブランドのアイテムまで取り扱うようになったのはなぜか——運営するショップ&カフェ「縁日」で、4代目の蜂谷悠介さんにお話を伺いました。
伝統文化を現代に伝える「京屋染物店」
——並んでいる「縁日」のアイテムを見ていて、一つひとつ丁寧に作られた手仕事の雰囲気が伝わってきます。もともと、お祭りの半纏(はんてん)や浴衣を長く作られてきたんですよね。
はい。創業以来、民俗芸能の衣装なども含め、全国からのオーダーに対して受注生産を主軸してきました。ただ近年は、木村石鹸さんと一緒でOEM以外にも、自社製品を展開するようになっています。
「縁日」は2018年ごろから開発を始めました。東北地方の伝統的な野良着である猿袴(さっぱかま)をベースにした普段着『SAPPAKAMA』が、2019年のグッドデザイン賞を受賞して以降、オリジナルブランドとして積極的に押し出しています。
 先人の知恵と工夫が生んだ機能美を、今の暮らしに落とし込んだズボン『SAPPAKAMA』
先人の知恵と工夫が生んだ機能美を、今の暮らしに落とし込んだズボン『SAPPAKAMA』
——アイテム数、すごく増えていますよね。
オリジナルアイテムだけでも、細かいものを含めるとかなりの数になります。他に、木村石鹸さんのように仕入れて販売している商品もあるので、全部でどのぐらいあるのか正直僕もわかっていません(笑)。
当初は開発に関わっていましたけど、今はほとんど社員に任せてますね。扱うジャンルも決まりはなく、基本的な方向性だけは共有しておいて、「この方角だったら何をやってもいいよ」としています。各部門から「やりたい」という人が集まってきて始まることも多いです。
京屋染物店 代表取締役の蜂谷悠介さん
——ブランド運営で大事にしていることはありますか?
商品の背景のストーリーをしっかり伝えることですね。そのアイテムはどんな文化に根差しているものなのか、どんな人のどのような技術が活きているのかを知ってもらうことに、力を注いでいます。ただカッコいいから作って売る、みたいなことはしていなくて、何かしらの社会的インパクトや価値を生むモノづくりができるといいなと。
たとえば昨年開発した『マタギもんぺ』。これは狩猟を生業としてきた山の民「マタギ」を継ぐ若い人たちから、先人たちの履いていたもんぺを復活させたいと相談を受けて始まりました。かつてマタギたちが生活の中で使っていたものを、現代の暮らしの中でも履きやすいパンツとして蘇らせています。それをストーリーとしてきちんと伝えるため、一緒にクラウドファンディングも行いました。
アイテムの背後にある、そうした生活文化をいろんな人に知ってもらうことが、結果的に東北の文化について考えてもらうことにもなります。その良さをもう一回身近に感じてもらうなかで、結果的に商品が売れたらいいな、くらいに思っています。

300人を超える支援者から、1000万円以上の支援が集まった「マタギもんぺ 復活プロジェクト」
震災後に経験した「感謝」と「お金」の関係
——昔から、そういうモノづくりをしたいと思っていたんでしょうか?
小さい頃から、染物屋さんになりたいなとは思ってました。父親に跡を継げと言われたことはないですけど、周りにいた人たちからも「ゆうちゃん絵うまいよね、やっぱり染め屋の息子よね」みたいな刷り込み教育をずっと受けてきましたし(笑)、まあなるんだろうな……と勝手に考えていて。
一つ大きかったなと思うのは、父親の後を追うように入った美大のデザインコースがちょっと変わっていて、「いいデザインをするためには地域に取材に行け」という考え方だったんです。どれだけカッコいいデザインでも、その土地、その場所で大切にされていることからつくったものでなければ、本当に長く続くデザインにはなっていかない。だから、まずは現場で生活者の声を聞いてこいと。
——現在にすごくつながっている気がします。
実際そこで出たいろんな企画で地域の人に喜ばれることも多かったし、これはすごくいい取り組みだなと思っていました。今思えば、うちが先祖代々大切にしてきたのも、まさにその部分でしたしね。
でも一方で、地元で目にする、シャッター通りの工場でひとり汗かきながら染物をしている父親の仕事を、「あんまりカッコ良くないなあ」と感じる自分もいたんです。卒業後は、もうちょっとクリエイティブなことをやりたいと思って、デザインやIT系の仕事をしていました。
ただ「苦労かけたな」という思いはあったし、何より「自分が最後までやり続けたいと思う仕事ってなんだろう」とはずっと考えていて。この染物屋を無くしたくない気持ちも強くて、実家に戻りきちんと父親に弟子入りをしたんです。そこから8年間、職人として働きました。
——悠介さんの代になってからは、法人化し事業を拡大するなど変化も見られます。
父の急死で、2010年に経営を引き継いだんです。見つかったときはガンのステージ4で余命3カ月、頭が真っ白になりながら走り回っているときに、今度は東日本大震災がありました。あらゆるものがストップして、まさに泣きっ面に蜂というか、全て奪われた気分になりました。
でもその時に、僕の中でようやく“染物屋”としての本質が見えてくることがあって。最初、震災で全国のお祭りは中止、注文も全部キャンセルになって、「ああ、自分たちって誰にも必要とされていない仕事をやってるんじゃないか」って思っちゃったんです。ところが、被災地の人たちと実際会うと、「いや、今だからこそ俺らは祭りをしたいと思ってる」と言われました。
あれだけ散り散りになって、希望も何も見えなくなったからこそ、人に昔のことを思い出させてくれたり、子どもたちに楽しい思いをさせてあげたり、大人たちがこれからの未来を考えたりできる場が要るんだと。だから祭りも、それを支える染物屋もすごく重要だと、逆に励まされてしまったんです。自分だけ落ち込んでいる場合じゃないと思って、そこから岩手・宮城・福島の3都道府県の沿岸にある60以上の団体に、祭り装束を寄付して回りました。

——各地の団体、それぞれの衣装を再現して?
そうです。どこの団体のものも流されてしまっているから、昔の写真や動画をひっぱり出して復元して。そうすると、いろんなところで祭りが復活し始めるんですね。それがすごく爽快で、自分でもやりがいを感じていました。
するとある日突然、いろんな団体の方がマイクロバスでうちにやってきて、寄付した半纏姿でそれぞれの踊りを披露してくれたんです。で、請求書も出していないのに、茶封筒にお金を入れて渡してくれました。
受け取れないと断っても、「いや、ダメだ。お前んとこの会社が潰れたら、俺たちはどこにも顔向けできない」「何が何でも絶対、この会社を発展させて、世の中に残るようにさせなければならないんだ」と。そう言われて、お金って誰かの役に立てば感謝の気持ちにくるまれていただけるものなんだ、それが商売なんだ……と思えたことは、僕には大きな気づきでした。
結局モノづくりって、そういう人のご縁が形になったものなんです。その縁を誠実に、大切にしていれば、相手にきっと届くんだと思いましたね。ブランド名「縁日」の名前も、そこから生まれました。
暮らしの体現者となる新拠点「縁日」
——「縁日」のサイトでは、自社以外にもさまざまなブランドの商品を取り扱いされていますね。まさにご縁がつながった形だと思いますが、一方でどこか一貫するものも感じます。どうセレクトされていますか?
基本的な考え方としては、僕ら自身が“共感できるかどうか”を基準にしています。共感のポイントや切り口は、さまざまなんですが。
例えば木村石鹸さんの『12/JU-NI』だと、指通りとか使い心地の良さはもちろん、開発者の方の思い自体をすごく大切にしていますよね。本人のサインまで入れて、背景のストーリーをしっかり発信されている。そこで働いてる人の顔が見えることって、僕らとしてもすごく大事だったりするわけです。
あと、代々やってきた伝統を受け継ぎながらも、ゼロからブランドを立ち上げてきたことへのリスペクトもありますよね。お香スティックの「hibi」さんなどもそうですが、昔からある価値を新しく提案しようとしている方を応援することも、僕個人としては大切にしています。
「縁日」で木村石鹸POPUPを実施したときの様子
——ショップ&カフェとして、実店舗である「縁日」も2023年にオープンされました。
ブランドができたすぐ後、2020年の頃には、京屋染物店の本店とは別にどこかにショップ出せるといいよね、という話はしていました。ちょうどコロナ禍で空き物件も増えていて、最初は東京が候補だったんですよ。
でも、まだ地元に何にも浸透していないブランドがいきなり東京に出ても、どこか底力に欠けるような気がして立ち止まりました。僕の中で違和感があっただけじゃなくて、社員たちの間でも「ちゃんと地に足がついてから、外に発信すべきじゃないか」と話題になったんです。
また「縁日」のコンセプト的にも、どこか外のビルにポコっとテナントとして入るのは、少し違うんじゃないかと思いました。むしろ僕ら自身が、商品を通じて提案している暮らしの体現者になっていないと、説得力がないなって。一関に拠点を置けば、実際に狩猟をしたり畑したり、地域と一緒にお祭りをしたりできますよね。そうやって“文化をつくる”ということをやってる人たちが、「モノづくりを通して、こういう世界にしていきたいんだ」と発信し続けるほうが、強みを持つはずだと考えるようになりました。
——お店自体は、市街地から離れた山あいにあります。赤荻笹谷にしたのはなぜですか?
きっかけは偶然で、近くを散歩していた父親の同級生にばったり出会ったからです(笑)。空き家になっている物件の持ち主と知り合いだとわかって、連絡を取ってくれて……。でも、これもご縁ですよね。
ありがたいことに、この地域の人にはすごく応援をいただいています。オープンする前に住民説明会を開いたときは「こんな何もないところで大丈夫か?」と逆に心配もされながら(笑)、それでも思いを伝えました。いろんなイベントがあるたびにこちらから声もかけるなかで、今ではお店の仕込みも手伝ってくださったり、最近始めた農業では「こうやったらいいぞ」などいろいろ教えてもらったりもしています。
——いろんな方が出入りされる場所なんですね。
もともと、僕自身は「村をつくりたい」という思いがあったんです。自分が子どもの頃見ていた京屋染物店の本店って、本当にいろんな人が集まる場所で、祭りなんかの拠点もうちだったんですよ。公共施設みたいな場所で育ったという感覚が今も自分の中に残っていて、「たくさんの人がいろんなことをしている」ような空間がすごく心地いい。
そんな僕が場所をつくるんだったら、やっぱりいろんな人たちによる生態系がそこに自ずと生まれていくようなことをしないとって、ずっと思っていたんです。場所がないからとか、田舎だからとか、お金がないといった制約を外せることが、「村」の中心になっていく京屋染物店の役割だろうなと考えています。
人の「思い」が事業を生み出す
——蜂谷さんの描く「村」の完成は、いつ頃になりそうですか?
今もずっと変わり続けてますしね……完成しないんじゃないでしょうか(笑)。地域の農家の方々には「俺らが年くったら、あとは京屋さんたちにまかせっから」 みたいなことも言われてますし、村だったら宿泊施設もやりたいし。
もちろん全て自分たちでやる必要はないから、最近は物件と人をつなぐ仲介のようなこともしています。今は使っていない家でも、地元の方々って「売れるなら誰でもいい」とは思っていないんですね。そこを信頼関係のある僕らが一回間に入って、フィルターになっていけると、新しい人が入りやすい環境がつくれると考えています。

——京屋染物店のような地元企業の支援があると、お互いに安心ですよね。
パン屋があってもいいし、古民家ランドリーがあってもいいし、何だっていいんです。こういう地域でチャレンジしたい人に向けた、創業支援の活動もしています。逆に大手企業による、サテライトオフィスの可能性だってある。イノベーションがいくつも創発していくようなビオトープになればいいなと思っています。
もちろん社員に対しても、商品開発と同じで一定の方向だけ示してはいますが、その中だったらどんな事業でもありにしてるんです。何をやるかよりも、その人の思いを見ていますね。このお店だって、今のメンバーがいなきゃこの空間はないし、フードメニューも生まれていないですから。
——木村石鹸でも、伊賀工場の社員たちが農業を始めたんですよ。「アグリクラブ」っていうんですが、そのスタッフがここに学びに来たいって言いそうだなと思いました。
ぜひぜひ交流しましょう。学び続けることってすごく大事だし、そのために必要なお金は僕もできるだけ社員に出してあげたいと思っています。
でも、やっていること自体が本人の喜びになっていけば、人は勝手にどんどん学んでいくな、とも感じているんですよね。結局、商品でもサービスでも、生み出すのはそこにいる人です。だから木村石鹸さんもそうですけど、やっぱり人を大切にしていける会社とのご縁を、これからも深めていきたいなと考えています。
——こちらこそ、これからもよろしくお願いします。今日は貴重なお時間をありがとうございました。