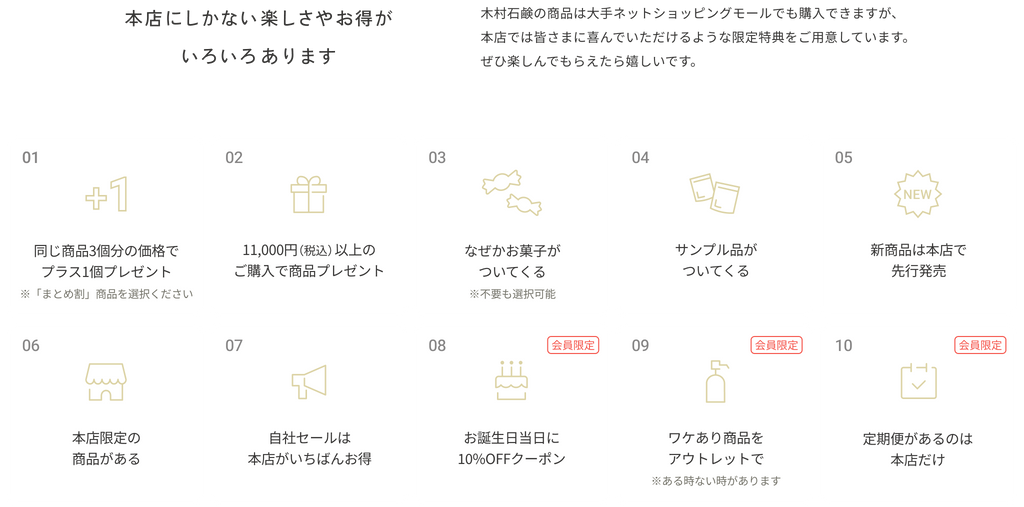インタビュー
きれいで、清潔で、きもちのいいお風呂を沸かすー小杉湯の原点
小杉湯の三代目平松佑介さんに取材させていただきました!

書き手:うらちゃん
2024年4月、ストリートカルチャーと若者文化の発信地である原宿に誕生した「ハラカド」。
その中には老舗の銭湯「小杉湯」の看板がありました。
今回は昭和八年から運営されている高円寺小杉湯についてや、
原宿に新たに誕生した小杉湯原宿についてなどを、小杉湯の三代目平松佑介さんに取材させていただきます。
小杉湯さんと木村石鹸との関わりはさかのぼること7年。
現在では、12/JU-NI(ジューニ)やSOMALI(そまり)をお取扱いいただいています。
平松さんには、家訓についてや銭湯の役割、木村石鹸との関係などについてお伺いしました。
平松佑介(ひらまつゆうすけ)・小杉湯三代目 株式会社小杉湯代表、株式会社ゆあそび副代表昭和8年に創業し、国登録有形文化財に指定された老舗銭湯「小杉湯」の三代目。2020年3月に「小杉湯となり」、2024年4月に「小杉湯原宿」を開業。モットーは「きれいで、清潔で、きもちのいい」お風呂を沸かすこと。 |