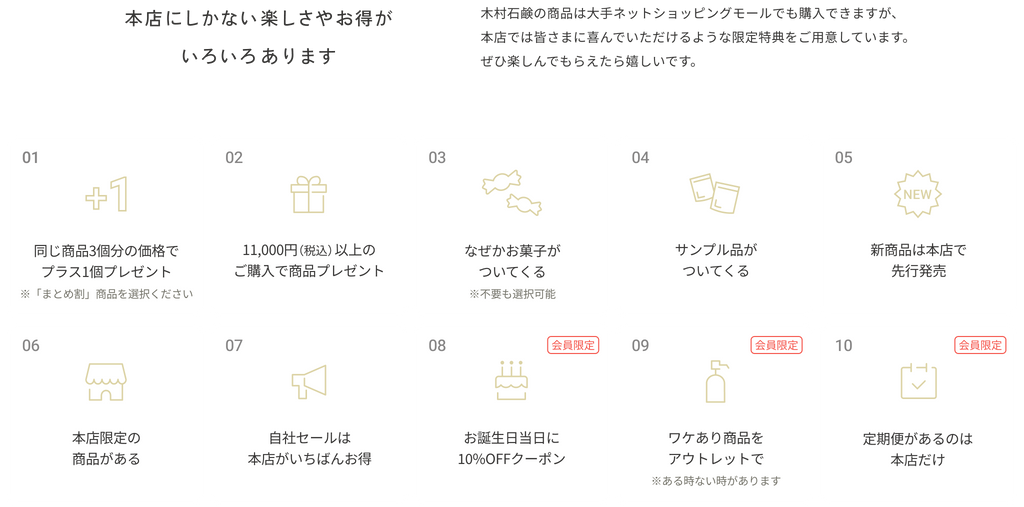インタビュー
【前編】クラフトプレスの誕生と藤原印刷の挑戦
一冊一冊心を込めて本をつくる藤原印刷の専務取締役の藤原隆充さんと、「ぬいぐるみのおふろセット」なども担当された営業の小池さんに話をお伺いしました。 【前編】では、藤原さんに家業である藤原印刷に入社した経緯や、ご兄弟との関係性、「難しい本をつくるなら藤原印刷」というイメージが出来上がった経緯についてお伺いします。
5月に長野県松本にある栞日さんで、新調した移動販売車 グットラックでの物販イベントと、藤原印刷さんも交えてトークイベントを実施させていただきました。
今回の記事は、一冊一冊心を込めて本をつくる藤原印刷の専務取締役の藤原隆充さんと、「ぬいぐるみのおふろセット」なども担当された営業の小池さんに話をお伺いしました。
【前編】では、藤原さんに家業である藤原印刷に入社した経緯や、ご兄弟との関係性、「難しい本をつくるなら藤原印刷」というイメージが出来上がった経緯についてお伺いします。
▼藤原印刷
藤原印刷は、長野県松本市に本社を置く印刷会社で、出版印刷、商業印刷、各種印刷物の企画・製作・デザインを行っています。1955年に創業し、作り手の要望に寄り添い、複雑な造本や手製本などを得意としています。https://www.fujiwara-i.com/
▼グットラックツアーの詳細(記事に埋め込み)
聞き手:にしうら
ー
本日は、専務取締役の藤原さんと「ぬいぐるみのおふろセット」をご担当された営業の小池さんお二人に取材させていただけるとのことで、ありがとうございます。よろしくお願いいたします!
藤原・小池
よろしくお願いします!
プロフィール ■藤原 隆充(写真右) 1981年生まれ。東京都国立市生まれ。大学卒業後コンサルティング会社、ネット広告のベンチャー企業を経て家業である藤原印刷へ入社。企画段階から仕様の提案を得意とし、個人法人問わずアイデンティティを込めた本づくり「クラフトプレス」を全面的にサポート。印刷屋の本屋(2018)、工場を開放した体験型イベント「心刷祭」(2019)、など様々なサービスを立ち上げる。共著に『本を贈る』(三輪舎 2018年)。二児の父。趣味は読書、知らない土地へ行く、構造を考える。 ■小池 潤(写真左) 旅行会社でのカウンター営業・web制作などの経験を積み、中国の上海勤務を経て2014年「藤原印刷」へ。本社営業部配属後、現在は富士見森オフィスを活用した八ヶ岳営業所を開設。木村石鹸の『ぬいぐるみのおふろセット』内の絵本の印刷コーディネーターを担当。 |
藤原印刷に入社した経緯
ー
確か藤原さんは東京で育って、大人になってから松本に移住されたと聞いています。
家業を継ぐためだったと思いますが、子供の時から「松本で働くぞ!」と思っていらっしゃったんでしょうか?
藤原
全然家業を継いで松本に・・とは思ってなかったです。
両親から「継げ」って言われたこともなくて。
おじいちゃんおばあちゃんも、お父さんもお母さんも、家族中が藤原印刷に勤めている人しかいなかったから「大人になったら僕も入るのかな~、どうなのかな~?」ってなんとなく思っていたのが幼少期ぐらいですね。
藤原印刷を創業されたおばあさま
それで、高校卒業して大学に行くときに進路を選ぶじゃないですか。
もちろん、商学部や経営学部と経営に直結する学部も考えたけど、本当に自分で継ぎたいと思ったこともないし、本当にやりたいことってなんだろうなと思ったときに出てきたのが心理学部だったんですよ。
ー
なぜ心理学部を志望されたんですか?
藤原
僕が中高男子校で、もうとにかく大学でモテたかったんです(笑)
モテるための最速の道筋は、人の心理が分かることだと思ってたんですね。
ー
なるほど(笑)
藤原
人の心がわかれば絶対モテるだろうと思って、心理カウンセラーの仕事を目指そうと思って、
近くのクリニックに飛び込みして・・・
「どういうお仕事ですか?」と聞いたら「1日20人ぐらい心に傷を抱えているの人と話をするんだよ」と教えてもらって、自分が想像していたこととは全く違うことがわかりました(笑)
それで結局商学部にしたんです。
大学に行って、社会人になっても(藤原印刷に)入れって言われなかったんで、家業と全然違うフランチャイズのスーパーバイザーっていう仕事をして、そのあとネットベンチャーのアイレップっていう会社に勤めました。
で、僕が青山のネットベンチャーでふわふわしてる間、弟は両親に「藤原印刷に入れてほしい」と懇願していて、でも両親は「長男が入ってないのになんで次男いれるんだよ!」と断っていました。
兄の僕が入らないと自分が入れないことがわかったので、地元の焼き鳥屋で「兄貴が入らないおれが入れないからいい加減行ってくれよ」と言われたんです。、「そんな思いさせてごめんな・・・」と翌日に退職願を出して・・というのが直接的なきっかけですね。
兄弟の関係性
ー
弟さんとの関係性も面白いですね。
兄弟は仲良かったんですか?
藤原
ちっちゃいときは喧嘩ばっかしてましたけど、社会人になってから仲良くなりました。ネットのベンチャーの会社のときには弟にインターンを頼んだこともあります。
ー
それは、いつか一緒に藤原印刷でお兄ちゃんと一緒に働きたいみたいなところがあったんですかね?
藤原
そうですね。
なのに、兄がずっと青山でふわふわして合コンばっか行ってるから(笑)
だらしない兄と、しっかりものの弟っていう関係性ですね。
弟は、大学1年のときから銀座の人材系のベンチャーでカバン持ちを始めていたので19歳の時から社会人経験がありました。たしか大学3年生のときにインターンに誘って1年ほど一緒に仕事してましたね。
難しい本をつくるなら藤原印刷という印象をもたらした出来事
ー
今では「クラフトプレス」という言葉を作られるほど独立系の出版物を手掛けられていて、難しい本の印刷といえば藤原印刷さんみたいな印象があるのですが、藤原さんが入社される前から独立系出版物をされてたのでしょうか?
藤原
全然やってなかったです。
祖父母や両親が何を印刷しているかも知らなかったし、入社してやっと「あ、本を印刷してるんだ」とわかったくらい。
僕は2008年、弟は2010年に入社したんですけど、業績はありがたいことに安定していました。
経理畑出身の母親が経営を引き継いで、感覚的な経営から財務体制を整えたことで、売上は横ばいだけど、内製化して粗利を上げて、非常に盤石な状態になっていました。
すごくありがたいことです。
ただ、その当時の僕は「お先真っ暗だな」と感じていました。
活字離れやデジタル化、書店減少などで、本の需要が増える要素がひとつも見当たらない。
このままやってもいずれ頭打ちがくるだろうし、何かを変えたいけど変え方がわからない。
例えば電子書籍やグラフィックデザインをはじめるなど安易な打ち手をやっては効果が出ない期間が3~4年は続きました。
ー
そのころのメインは何だったんですか?
藤原
メインの印刷物は専門書・参考書で、法律系・税務系・教育関係などの専門書です。
ー
実用書や参考書がメインだったんですね。
何をやったらいいかわからなくなっていたときに、どうやってやるべきことが見えてきたのでしょうか?
藤原
ずっともがいていて、何か変えなきゃいけないっていうマインドだけは常に働いていました。
変わるきっかけになったのは、東京で営業をしていた弟に「印刷会社が理由で作りたいものが作れない」という声がデザイナーさんから数件聞こえてきたことからです。
印刷業界では「水と空気以外は印刷できる」と言われてきたのに、「何でそういうことが言われてしまうんだろう」と思い、やってみようかと考えたのがターニングポイントになっていきました。
中でも印象的なお仕事は、青山ファーマーズマーケットを運営している会社さんの「NORAH」という雑誌です。
当初の要望は「160ページの本を1ページ1ページ全部違う紙で作りたい」というもので、しかもその紙は全国の印刷会社に眠っている紙を集めたいと言われました。「えっ?」って感じですよね(笑)
でも、どんな難しいオーダーでも「NO」と言わないようにしようと兄弟で約束をしていました。
本は1ページずつ印刷しているわけではなく、大きな紙に沢山ページを配置して、それを2回3回折って、小さな冊子を順番に並べて本になります。、その小さな冊子はだいたい16ページです。
それを利用すると16ページごとに紙を変える方法なら1ページごとに紙を変えるよりもだいぶ現実的になります。さらに紙の順番を変えて最終的には48パターンになる提案をしたところ採用となりました。
クラフトプレスという言葉に込めた意味
ー
クラフトプレスという言葉を打ち出されたのは最近だと思いますが、改めてどういった想いからこの言葉をつくられたのか、お伺いしてもよろしいでしょうか?
藤原
自費出版という言葉は昔からありますよね。
次に出てきたのがZINEやリトルプレスです。
ZINEは元々アメリカのストリートカルチャーから出てきたものでコピー機で刷って、ホッチキスで留めて、荒々しさが魅力な印象です。
リトルプレスは文字通り「少部数」の印象が強くて、例えば5000部はリトルとは言えないよなあと感じていました。
何かこれらをまとめる良い言葉がないかと考えてたとき、クラフトビールの「ヤッホーブルーイング」さんがこれまでのキリンさんやアサヒさんのラガー一強から、パッケージも味も個性的なビールをつくってが人気を得ていたことにピンときました。
規模にとらわれず、個性的で自分が良いと思うものを作る動きが、クラフトビールやクラフトジンと共通するので「クラフト」という言葉をつけようとまず思ったんです。
次に、「ブック」だと名詞で本そのものになってしまうので、「つくる(=出版する)」という動詞にしたくて、クラフトパブリッシングかクラフトプレスの二拓になり、最終的に響きの良いクラフトプレスになりました。
ー
たしかに、クラフトプレスっていう言葉の響きがすごくキャッチ―なので、もともとあるものかと思っていました。
藤原
僕らの場合は、本を作る際の紙や色を選んだり、工場を見にきたり、オペレーターと話しながら決めるような、プロセス全体を楽しんでもらえるので、「みんなで本を作ろう」という動きを表現する動詞がマッチするんですよね。
〉〉後編へ続く